勤労感謝の日は1948年に制定された国民の祝日の1つで
「勤労を尊び、生産を祝い、国民が互いに感謝しあう日」、
とされていますが、
以前は「新嘗祭(にいなめさい)」と言われていました。
なぜ名称が変更されたかというと、
日本がアメリカとの戦争に負けたからです。
日本の古くからあるしきたりや習慣を消し
欧米の習慣に変えようとする占領政策の1つでした。
目次
新嘗祭とは?
新嘗祭とは、その年の五穀の収穫を神様に感謝して
お祝いする風習で今も続いている、
古来からある皇室の大事な行事の1つです。
儀式として形が定まったのは
飛鳥時代の皇極天皇の時。
その年の新穀を天皇が神様に捧げ、
自らも食します。
今では廃れてしまいましたが、
民衆もこの日まで新米を口にしない
習慣がありました。
当日は宮中で天皇が1人正座され神様と向き合います。
1度の祈りは2時間。
それを2回、合計4時間に及びます。
毎年1300年以上続いている皇室の重要な神事なのです。
また、天皇が即位の礼の後の最初の新嘗祭のことを
大嘗祭(だいじょうさい)といいます。
今上天皇の大嘗祭は1990年(平成2年)のことでした
(その年の11月12日が即位の礼)。
もともと日本は豊かな自然に恵まれた農業の国。
収穫を感謝する習慣は民衆にとって自然に生まれ、
国の大事な行事となっていたのです。
[ad#co-1]
このような収穫を感謝する習慣は
世界中で見られます。
世界の勤労感謝の日
秋になると多くの地域で似たような祭りが開かれます。
オクトーバーフェストは、
ドイツの有名な収穫祭。
日本でもすっかり広まったハロウィンも、
もともとはケルト民族の収穫感謝祭でした。
アメリカには9月の第1月曜日に
レイバーデイ(Labor Day:勤労の日)という
日本でいうとメーデーのような行事があります。
また、新嘗祭のような収穫を感謝する
「Thanksgiving」(感謝祭)が
11月の第4木曜日に行われます。
占領国軍(GHQ)はこの2つをあわせた
「Labor Thanksgiving Day」という名称を
考案しました。
その日本語訳が「勤労感謝の日」ということなのです。
[ad#ad-2]
その他の変更された祝日
このように他の祝日でも神事と深い関わりがあると
判断された祝日の名称は変更を
余儀なくされました。
2月11日の「建国記念の日」も元々は「紀元節」でした。
「日本書紀」の記述を基に初代天皇の神武天皇が
即位したと決められた日です。
「春分の日・秋分の日」も
「昼と夜の長さが同じ日」として知られていますが、
本来は「春季皇霊祭・秋季皇霊祭」という
皇室の先祖の霊を慰める重要な神事が行われる日です。
このようにいくつかの祝日の中には、
本来の日本の姿が隠れているのです。


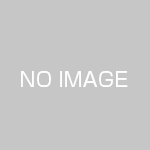
この記事へのコメントはありません。